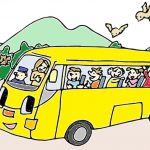2010年代後半から、日本の社会では政府によって提唱された「働き方改革」に基づき、様々な仕事場で労働環境改善への取り組みが急務となりました。
この改革の根拠となっている法律は2018年の通常国会で成立し、2019年4月から段階的に施行がはじまった「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」ですが、この法律ができるまでには長い期間がかかっています。
働き方改革のルーツとなっているのは、2000年代後半に提唱された「労働ビッグバン」とよばれる労働市場改革です。
当時の経済財政諮問会議にて提唱されたこの改革にはワーク・ライフ・バランスの実現や高齢者・女性の就業率向上、雇用における正規・非正規の区別の撤廃、法律による同一労働同一賃金の制度化、ホワイトカラー・エグゼンプションの導入など、現在の働き方改革関連法において盛り込まれている内容が数多く盛り込まれています。
労働ビッグバンを実現するための法案は2007年につくられ、国会にも提出されましたが、年金記録問題が大きな社会問題となり、その対応に力を注がざるを得なくなったため成立させることができませんでした。
しかし、この労働ビッグバンで提唱された政策はその後個別に国会で審議され、成立していきます。
2007年12月には労働契約法が制定され、その中で有期労働契約を期間の定めのない労働契約に転換可能にするルールなどが定められました。
2012年には国会で年金機能強化法案が成立し、パートタイム従事者も一定の条件を満たせば厚生年金への加入が可能になりました。
この法律では年金の受給資格期間の大幅な短縮も行われ、それまでパートタイマーとして長く働いていたのに年金を受け取る資格がなかった人も年金を受け取れる可能性がひらけました。
2014年になると、ワーク・ライフ・バランス実現の施策として、過労死やそれに結びつくおそれがある疾患などの発生を防ぐために国や地方公共団体、企業などが取り組むべき事項を定めた過労死等防止対策推進法が成立しました。
2015年から約3年ごとに策定されている過労死等の防止のための対策に関する大綱は、この法律に基づいてつくられています。
2015年の通常国会では、政府が高度プロフェッショナル制度創設やフレックスタイム制・裁量労働制の見直し、年次有給休暇の取得義務などを盛り込んだ法案を国会に提出しました。
しかし、過労死やサービス残業の横行を招くおそれがある内容となっていることから、法案が提出された段階で根強い反対があり、他の法案の審議が優先された影響もあって2年以上にわたって事実上の店晒しの状態が続きました。
この提出法案は2017年9月末の衆議院解散により、慣例によっていったん廃案となりましたが政府は諦めず、法案の構成を見直した上で2018年の通常国会に働き方改革を実現するための法案として再度提出しました。
これが「働き方改革関連法案」です。
働き方改革関連法案は、2018年の通常国会において内閣の最重要法案に位置づけられました。
審議では、野党議員を中心に法案の立て付けや実効性そのものの問題が数多く指摘されたほか、厚生労働省が行った裁量労働制に関する調査の結果においてデータに捏造の疑いが見つかり、法案から裁量労働制に関わる部分を削除する事態も起こりました。
しかし、通常国会での成立にこだわる与党は両院で圧倒的な多数派を維持しているのを利用して審議日程の消化を続け、6月末に参議院本会議において賛成多数で可決し、法案が成立しました。
2000年代後半から提唱され続けてきた労働市場改革は10年あまりの期間をかけて大部分が法制化され、現在に至っています。
最終更新日 2025年5月20日 by packet